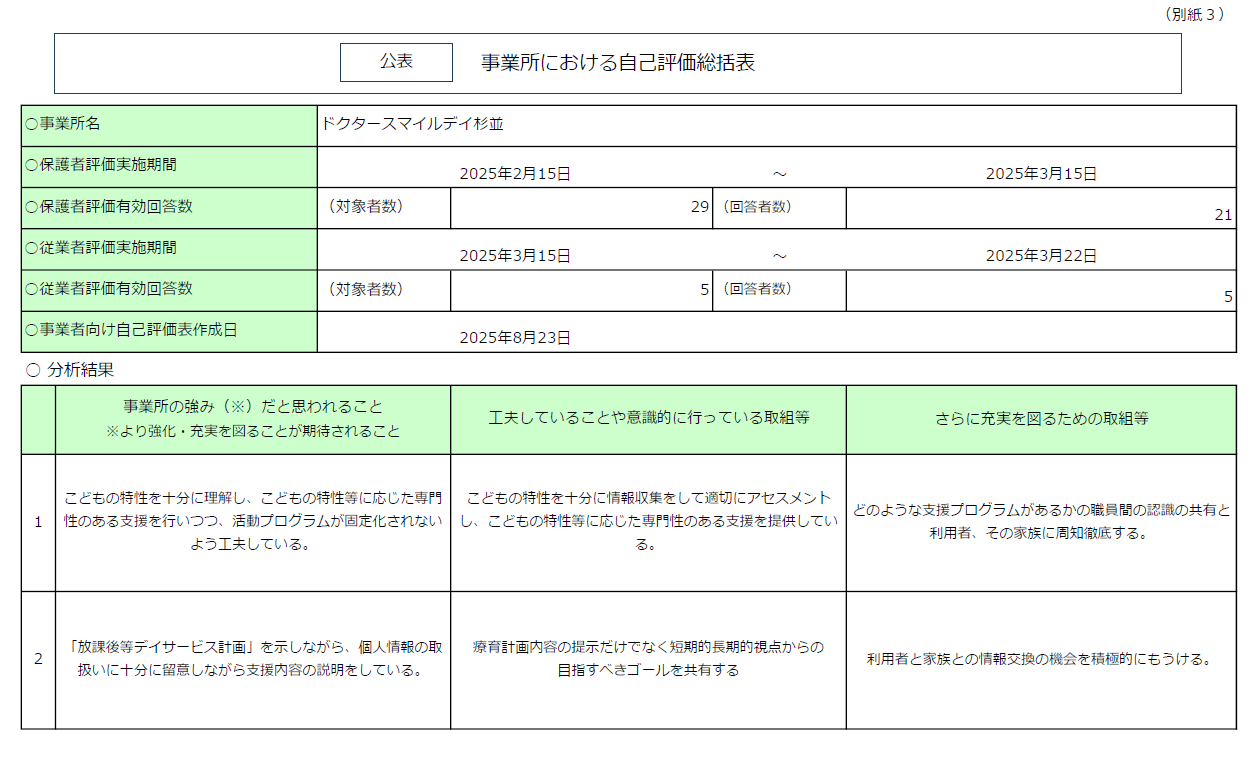「この子は、普通級と支援級、どちらが合っているのだろう…」
就学や進級のタイミングで、発達に特性のあるお子さんを育てるご家庭がぶつかる、非常に大きなテーマです。
✅ 発達障害があるからといって、必ずしも支援級が適しているとは限りません。
✅ 一方で、「なんとか普通級で頑張らせたい」と無理をしてしまうことで、お子さんが苦しむケースもあります。
今回は、ドクタースマイルデイ杉並の支援現場から、どちらを選ぶか迷ったときの考え方や判断軸について、分かりやすくお伝えしていきます。
✅ 普通級・支援級の違いとは?
まず基本的な違いを簡単に整理しておきましょう。
普通級では、学年ごとの学習指導要領に沿った授業が行われ、支援はあくまで“配慮”の範囲内となります。
一方の支援級(特別支援学級)は、少人数での授業が基本となり、子どもの特性や理解度に応じた個別支援が提供されます。
ですが、実際の現場はその“枠”だけでは語れません。
同じ「普通級」であっても、学校や担任の先生によって支援の質や柔軟性は大きく異なります。
✅ つまり、“制度上の違い”ではなく、“その子にとって合っているかどうか”が重要なのです。
判断軸①「集団の中で安心できるかどうか」
「周りの子たちについていけるか」「勉強がどれくらいできるか」
こうした基準で級を決めようとする保護者の方は多いですが、実はもっと大切な視点があります。
それは、その環境で“安心して過ごせるかどうか”です。
・大勢の中にいると、緊張して発言できない
・座っていられるけれど、内容が理解できていない
・表面上は問題なく見えるが、家に帰ると大荒れになる
こうした子どもは、外からは「うまくやれている」と見えることが多いですが、実は大きな負荷を抱えていることも少なくありません。
支援級は“できない子が行く場所”ではありません。
✅ 安心して自分を出せる場所を用意するための選択肢なのです。
✅ 判断軸②「困りごとを言葉にできるか」
大人からの観察だけでは分からないことも
子ども自身が「ここがつらい」「こんなふうにしたい」と言える場合は、環境に対する希望を汲み取りやすくなります。
しかし、発達障害のあるお子さんの中には、自分の困りごとをうまく言葉にできないケースも多くあります。
そのため、日常の様子を丁寧に観察することが大切です。
・学校から帰ると極端に疲れている
・行き渋りが続いている
・自己否定的な発言が増えてきた
こうした兆しは、「環境が合っていない」サインかもしれません。
当施設にも、普通級でがんばっていたけれど、周囲との差を感じて落ち込むようになったという相談が寄せられます。
その子に合った環境で過ごすことで、少しずつ自信を取り戻していく姿も、多く見てきました。
親の「想い」と「現実」をすり合わせることも大切
「同じ地域の子と一緒に過ごさせたい」
「できるだけ普通の環境で育ってほしい」
その気持ちは、どの保護者の方も持っていて当然です。
ただ、その想いが“今のお子さんの状態”とすれ違ってしまうと、支援が届きにくくなることもあるのです。
✅ 判断は「この先ずっと」の決断ではありません。
学期ごと、学年ごとに見直すこともできますし、普通級と支援級を行き来する“交流支援”のような仕組みもあります。
大切なのは、「今、この子が安心して学べる環境はどこか?」という視点で考えること。
一人で悩まないで、相談できる場を持つ
発達障害のお子さんにとって、早期発見と適切なサポート方法はその後の生活を大きく左右します。
とはいえ、親だけで「普通級がいいのか」「支援級にしたほうがいいのか」と悩み続けるのは、とてもつらいことです。
私たちドクタースマイルデイ杉並では、医師が常駐し、発達に課題を抱えるお子さん一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングしています。
✅ ご家庭と連携しながら、進学や就学にまつわる不安にも寄り添い、選択肢を一緒に整理するお手伝いもしています。
📩 「このままでいいのか」と感じたときが、相談のタイミングです。
ご家庭で抱えているお悩みを、どうぞ一度私たちにお聞かせください。
#発達障害 #早期発見 #適切なサポート方法 #支援級 #普通級 #就学相談 #進路の悩み #発達支援 #特別支援学級 #学級選択 #支援の判断軸 #学校生活の困りごと #家庭との連携 #ドクタースマイルデイ杉並 #療育支援 #学習環境調整 #交流支援 #子育ての悩み #不登校傾向 #環境選びのコツ